どうもこんばんは、ループの螺旋階段です。御朱印集めをこれから始めようとされているから向けに、気になることや疑問に思われそうなことを解説する記事の2回目です。1回目である前回は御朱印集めを始めるにあたっての準備についてまとめました。
御朱印巡りの始め方〜御朱印帳の両面使い・寺社混合、初心者の疑問を解決!〜今回は実際に御朱印巡りを行う際のマナーや手順についてまとめています。寺社は信仰や宗教に関わる施設ですので、参拝者や寺社の方々に迷惑を掛けないような最低限のマナーは絶対に守るべきだと私は考えています。
スポンサーリンク
この記事の目次
御朱印巡りに際しての心得
前回の記事にも記載していますが、とても大切なことなので改めて書きます。御朱印というは「参拝をした証」にあたるものです。観光地の記念スタンプとはかなり意味合いが異なります。ただ単に集めるのではなく、宗教行為にあたるという側面があることは理解をしてください。
参拝もせずにひたすらに御朱印を集めるのでは本末転倒です。また、他の参拝者や寺社に迷惑をかける行為はもってのほかです。繰り返しですが、この点だけはご認識をお願いします。
最初に重々しく書いてしまいましたが、その点さえ配慮してもらえれば、楽しみながら寺社を回ることはむしろ好ましいことですので気軽に楽しく始めましょう。
御朱印をいただく手順
では、実際に御朱印をいただく手順の解説に移っていきましょう。
まずは参拝する
まずは参拝です。御朱印はその寺社を参拝した証にいただくものです。このため、参拝をせずに御朱印をいただくという行為はNGです。
参拝後に授与所もしくは社務所へ
まずは参拝して、その後境内にある授与所もしくは社務所で御朱印をいただきましょう。担当の方にお願いをする際は、御朱印をいただきたいページを開いて状態で御朱印帳を渡してください。
ここで寺社によって対応が3パターンに分かれます。1つはその場で書いていただけるパターン。もう1つは一旦預かりとなり、完成後に受け取るパターンです。後者の場合、引換札による対応となりますが、自分の御朱印帳を取り違えないように注意が必要です。
また、最後のパターンとしてその場で書いていただけな場合は、書置きをいうすでに御朱印が書かれた紙を受け取り、自分で御朱印帳に貼り付けることになります。
初穂料を納める
御朱印をいただくにあたり、納めるお金は初穂料(はつほりょう)と呼びます。多くの寺社でお金が明示されていて、300円~500円というところが多いです。
一部の寺社では「お気持ちで」と言うところもあります。こうなると困ってしまうのですが、一般的な金額に合わせて300円~500円をお納めすることが無難です。
御朱印をいただける時間
参拝が可能な時間と御朱印の対応が可能な時間は異なるので注意が必要です。一般的には9時もしくは10時に開始して16時もしくは17時に終了するパターンが多いです。ただ、寺社によって異なるので事前の確認をオススメします。
また、寺院によっては丸1日御朱印対応の無い日も設定されているため、こちらも確認が必要です。加えて注意が必要な点として、小さな寺社では昼食時に受け付けていない場合もあります。
スポンサーリンク
御朱印をいただく際に守るべきマナー
続いて、初心者の方が気になるマナーの解説です。
御朱印をいただく前に参拝して良いのか?
先ほども書いた通り、御朱印は参拝をした証なので、参拝をした後に御朱印をいただく方が正しい順番です。私も可能な限り、参拝後にいただくようにしています。ただ、混雑状況によっては先に御朱印をいただくことも問題ないかな個人的には考えています。
特に最近は観光バスなどで大量の人が行列を作るケースも有るので、到着した時点で空いていそうなら、先に御朱印をいただくパターンもありです。ただ、その後に参拝することは忘れないようにしてください。参拝をしないと御朱印を貰う意味がぼやけてしまい、意味がなくなります。
御朱印帳を渡す際は書いて欲しいページを開く
御朱印は基本的に御朱印帳のどこのページにいただいても問題ありません。なので、自分で書いていただきいページを開いてお願いをするようにしましょう。
御朱印をいただいている間の待ち方
目の前で順番に書いていただくのを待つパターンと、番号札を渡して待つパターンの2つがあります。
どちらのケースも寺社内なので、他の参拝者の方の迷惑にならないように静かに待つようにしましょう。特に、目の前で書いていただく際にスマホ等をいじって待つのも失礼に当たるのでNGです。
初穂料は大きなお金で払わない
また、1万円札や5千円札と言った大きなお金はお釣りの対応で先方に負担を掛けるので避けたほうが良いです。相手の方を困らせないためにも小銭を用意しておきましょう。
受付時間外は諦める
御朱印を貰える時間と参拝時間は一致していない場合もあり、寺社に着いた際は受付時間外というケースもあると思います。また、大きくない寺社では急遽お休みというケースも有ります。
この場合に、どうしても御朱印が欲しいからと言って受付時間外に寺社に隣接する住宅のインターホン等を鳴らしてお願いするのは絶対にNGです。寺社の方にも生活があります。最低限のマナーは守って御朱印集めを楽しみましょう。
担当者がいない場合は?
規模が大きくない寺社では御朱印担当の方がいない場合があります。書き手がいない場合は、「書置き」という既に御朱印が書かれた紙を頂ける場合があります。書置きは御朱印帳の空きページに直接貼り付けていただいて問題ありません。
書置きもない際は残念ながら御朱印をいただくことはできません。ご縁が無かったと考えて、再度参拝する楽しみとしてとっておきましょう。
関連記事
御朱印巡りの始め方〜御朱印帳の両面使い・寺社混合、初心者の疑問を解決!〜 御朱印集め記 ~東京メトロ駆使編~スポンサーリンク
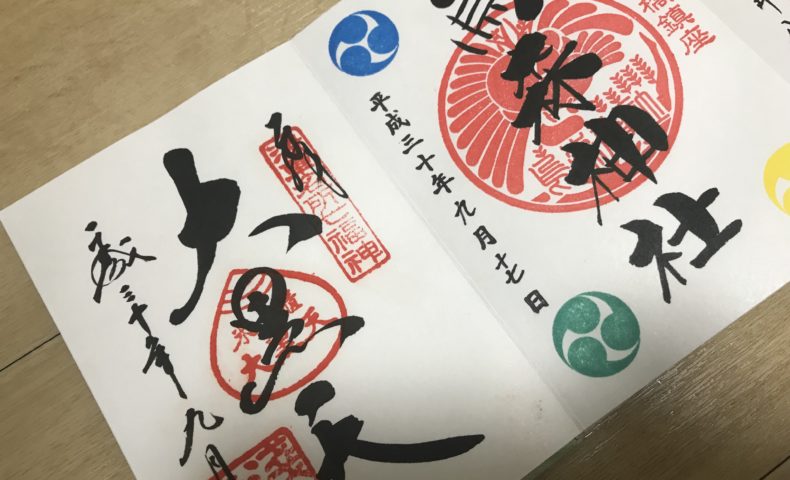


















この記事へのコメントはありません。